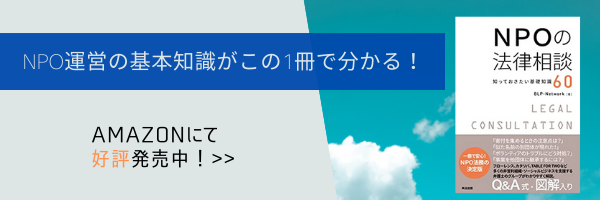契約書に関するご相談をお受けすることがしばしばあります。
通常は、どのような契約を結べばいいのか、この契約条項でいいのか、といった契約書の内容に関する質問が中心です。しかし、非営利事業を立ち上げられたばかりのスタートアップ段階の方からは「どこにどんなハンコを押したらいいですか?」「ホチキス止めはしたほうがいいですか?」というように、契約書の内容の前に形式面についての質問を受けることがあります。
そこで、今回は、契約書の形式面についての注意事項をまとめました。
1 題名
会社や団体、個人の間で取り交わされる書面には「契約書」「合意書」「覚書」といった様々なタイトルがついています。当事者間の権利と義務を定め、その意思が表明されている書面は、題名が「契約書」ではなかったとしても契約書としての性質があることになりますので、注意して内容を検討しましょう。
2 押印
(1)署名押印
契約書は、原則として両当事者が署名押印をして完成します。氏名(個人のとき)または名称(法人のとき)を自筆する場合のことを署名押印、氏名・名称が最初から印字されている場合のことを記名押印といいます。
法人が契約の当事者であれば、「特定非営利活動法人●●●● 代表理事●●●●」等と記載し、法人の代表印を押します。一方、契約当事者が個人の場合は、個人の名前と印鑑を押します。法人が契約当事者なのに署名押印が個人名でされているような契約書をたまに見かけますが、個人と契約をしたのか法人と契約をしたのかが不明確になってしまいますので気をつけましょう。
印鑑にはいろいろな種類があります。印鑑登録している印鑑のことを実印といいます。個人が契約当事者である場合、不動産の売買など重要な契約では実印の押印が必要ですが、通常は認印で問題ありません。
(2)契印
契約書が複数枚にわたる場合、左側2箇所をホチキス止めし、各ページを見開いた間の部分に契約当事者が割印をします。このことを契印と呼びます。契印は、ページが途中で差し替えられて契約書の内容が変わってしまうことを防止する趣旨で押しています。
3 製本
契約書を製本する場合は、左側2箇所をホチキス止めし、文房具店で売っている製本テープで固定して製本します。製本テープで製本した場合には、製本テープと契約書の間に契印をして、各ページの間の契印は省略するのが通常です。
4 通数
契約当事者が2人いる場合には、原則として同じ契約書を2通作成して、それぞれが1通ずつを保有します。ただし、差入式の契約書といって、A社とB社の間の契約なのに、B社だけが押印し、「A社 御中」としてA社に差し入れるタイプの契約書も存在します。この場合、B社としてはA社に対してどのような約束をしたかを後から確認できるように、手元にコピーをとっておいた方がよいでしょう。
5 印紙
契約書には印紙を貼る場合と貼らない場合があり、文書の種類・性質によって決まります。詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」で確認しましょう。下記URLの印紙税の解説のうち、印紙税額の一覧表(分類コード7140、7141)に課税対象となる文書の一覧が記載されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
例えば、「請負に関する契約書」は原則として印紙税の課税文書であり、例えば記載金額(請負金額等)が1万円以上100万円以下の契約書には200円の印紙を貼る必要があります。
この点、しばしば問題になるのが「業務委託契約書」です。よく見かける題名の契約書ですが、その内容が「請負に関する契約書」であれば印紙を貼る必要がある一方、「委任に関する契約書」であれば印紙を貼る必要がありません。「委任に関する契約書」は印紙税の課税文書ではないからです。
「請負」とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約のことをいいます。一方、「委任」とは当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約です。なお、法律行為以外の事務の委託をすることを準委任といいます。
例えば、建物の清掃をする業務を請け負った場合には、一定の仕事の完成に対して報酬をもらう内容の契約ですので、「請負に関する契約書」として印紙税を貼る必要がある文書といえるでしょう。これに対して、建物の維持・管理や省電力化に関するコンサルティング業務を提供する場合には、受任者側で一定の裁量を持って委託された事務を遂行する内容の契約であって、その結果よりも遂行過程が重視されることから、「委任(正確には準委任)に関する契約書」であり印紙税の課税文書ではないと考えることができます。
ただし、実際は微妙なケースも多いので、気になる場合には専門家に相談してみましょう。
弁護士 生田秀